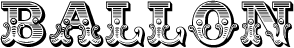2021年新春は2つのワルツで高雅で退廃的な時を
明けましておめでとうございます。喜び溢れる2021年となりますことを祈念しております。
さて始まった2021年。新春と言うとクラシック音楽の都、オーストリア・ウィーンでは毎年元日にウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(通称ウィーンフィル)によるニューイヤーコンサートが開かれる。場所はクラシックのメッカであるウィーン楽友協会。このまるでクリムトの絵画か!?と思わせるまばゆい黄金の意匠が施された歴史あるホールで世界のトップが年の始まりから腕を振るうのだ。
日本ではEテレでライブ中継され、しかも日本時間19時頃という最高の時間帯のため、チャンネルを回しているときに目にしたことがあるという人もいるだろう。今年は楽壇の帝王的存在リカルド・ムーティが指揮者として招聘。新型コロナウイルスの世界的流行により、無観客で実施された。
ここで演奏される曲が、“激ウィーン”なのだ!ヨハン・シュトラウス2世の『春の声』『青く美しきドナウ』など、ド直球のウィンナー・ワルツが演奏される。このプログラムはもともとナチスによりドイツに併合されたオーストリア市民の不満を和らげるためにニューイヤーコンサートが始まったためらしい。
社交界へ出る際には舞踏会の文化が未だあり、高雅で聴きやすいワルツの曲々はヨーロッパの貴族文化を今に感じる文化遺産だ。ロマンティックで煌びやかである円舞曲は正月の晴れ晴れしい気分に打って付け。部屋で飲食を楽しみながらゆったりと聴きやすいのも良い。誰もが一度は耳にしたことがある曲なので楽しく聴ける。
2002年には日本の国宝級指揮者小澤征爾が振った。
しかしちょっと軽すぎて嫌!という人もいるだろう。そういう人はフランス人が作ったウィンナー・ワルツをおススメする。フランスの管弦楽の魔術師モーリス・ラヴェルはシュトラウス2世のウィンナー・ワルツへの敬意から新しいワルツとして『ラ・ヴァルス(仏語でワルツの意)』を作曲した。
舞踏詩と穿たれるこの曲は、シュトラウス2世らにはない官能と瞠目と狂乱に満ちている。楽譜初版には、以下ラヴェルによる序文がある。
渦巻く雲の中から、ワルツを踊る男女がかすかに浮かび上がって来よう。雲が次第に晴れ上がる。と、A部において、渦巻く群集で埋め尽くされたダンス会場が現れ、その光景が少しずつ描かれていく。B部のフォルティッシモでシャンデリアの光がさんざめく。1855年ごろのオーストリア宮廷が舞台である。
最初は高雅なワルツなのだが、次第次第に酩酊しながら螺旋階段をくるくると踊りまわっていくかのように不協和音が鳴り、テンポが乱れていく。その有様は、場はさんざめき、シャンデリアは落ち、シャンパンの瓶が割れ、まるで狂乱の舞踏会場のようだ。そして突如曲が終始する!!!この構成は19世紀の濃密なロマンと貴族趣味が20世紀のリアリズムに取って変わられるのを象徴するかのように機械的なのだ。
『ラ・ヴァルス』の10分間はその壊れゆくオーストリア宮廷の音世界にずっと身をゆだねたいと思わせる蠱惑的な時間が流れる。
音と時間について考えさせられるマエストロ、セルジゥ・チェリビダッケの指揮で、異常にスローになり引き延ばされた退廃と官能の14分間を聞いてほしい。
ラヴェルは寡作な作曲家でスイスの時計職人と形容されるほどに1曲を玲瓏に磨き上げる音楽家だった。ゆえにどの曲も一分の隙もなく精緻に設計されている。人工美の極致なのだ。その冷たいまでに研ぎ澄まされた音列の裏に、熱くも醒めたラヴェルの美学が覗く。本音を言い表さず、その仮面の表情こそが本音のような、ラヴェルの作品たち。一聴でも心地よいが、繰り返し聴くことで味わいが増す、職人的工芸作品のようだ。肖像を見ると、端正な顔立ちでクールな印象。当時珍しかった電話での通話を好み、午後はカクテルタイムを楽しんだ。背格好は小柄で、化粧をして外出したというダンディ。冷たいようでチャーミング、本心が読めるようで読めない、不思議な距離感の音楽家なのだ。晩年は精神に障害が起こり、作曲出来なくなったことが残念でならない。
さて、ニューイヤーコンサートのプログラムはシュトラウス研究家などシュトラウスの権威が決めているのだが、ウィンナー・ワルツ以外にはその年アニバーサリーとなる作曲家がプログラムにセレクトされることが多い。また指揮者ゆかりの曲が組まれることもある。フランス人指揮者が過去招聘されたことがあるが、『ラ・ヴァルス』が演奏されたことはいまのところ無いようだ。そりゃオマージュと言えど、破壊された方からしたら断固拒否なのだろう(笑)。
by writer Mitsuhiro Ebihara