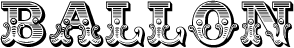薔薇香る三島由紀夫の死の官能
昨年2020年は、大文豪・三島由紀夫の没後50年だった。記念した映画が上映されたので観た人もいるだろう。
三島の文体は、華麗で、豪華絢爛で、ジョン・ガリアーノのディオールのオートクチュールみたいなテイストと例えたらなんとなく伝わるだろうか。装飾華美なことこの上ないのだ。代表作である『仮面の告白』『金閣寺』『豊饒の海』などどれも凄まじい。言葉と思想が漲っているというか、まず語彙力が尋常でなく、綴られる文一つひとつがハイジュエリーのように煌びやかなのだ!!三島の恩人である大文豪・川端康成とは対照的で面白い。川端は無駄が1ミクロンもない文体で、一つの事象を綴るのに最も美しい最小限の文章を書く。まるでアズディン・アライアのようなそぎ落とされた構築美なのだ。川端のような文章が書けたらなあといつも思う。
このように文体は正反対で親交のあった大文豪の2人なのだが、共通しているのは耽美的で死臭を放っていることだ。“デカダンス”の一言が最も似合う。
三島は小説家だけでなく、映画に出演したりと多才であり華やかだった。また身体を鍛え、筋骨隆々。身長は低かったがシークレットブーツでごまかしていた。作品からもスタイルからも、芸術家としてのナルシズムが匂い立つ。そのナルシズムの表出として、自身が被写体となった写真集が作られている。タイトルは『薔薇刑』。撮影したのは、日本写真界の重鎮中の重鎮、細江英公だ。28歳の細江は、彼の作品を見た三島に見出され、この異形な写真集を撮影した。
モノクロ写真に、鍛え抜かれた三島が様々なポーズで佇む。噎せ返る三島の美意識。マッチョで耽美的な男体。どことなく想起させる死。その強烈な天才と格闘する細江の画作り。芸術家同士の結晶なのだ。プリントは当時細江のアシスタントだった森山大道。独特のザラついた質感が当時から森山らしさを感じる。そして不気味だ。これまた耽美な写真集名は、細江が三島に相談し、挙げられた中から『薔薇刑』に即決したという。
存命中幾度もノーベル文学賞候補となった三島は当時から国際的に知られる小説家だった。この写真集も海外版が編纂されることとなった。大幅に内容が変更され、装丁を現在なお旺盛な作品制作を行っている美術家の横尾忠則が担当。薔薇が覆う、三島の涅槃像を描いたカバーなどナルシシズムの極みだ。
三島は戯曲家としても名高かった。そのため自分の思想を発露させるためにビジュアル媒体の強さを知っていたのだろう。彼が監督・主演した自作の『憂国』も美意識を存分に感じられる。美術は能舞台、セリフは一切なしで静的な男女二人の死が描かれる。BGMはワーグナーの性愛の官能を描いた音楽『トリスタンとイゾルデ』。日本の伝統芸能に西欧を代表する音楽が混ざり合い、死が官能へと昇華する!!美しい死を描いた三島の最後は、彼にとっての涅槃なのかもしれない。
さて薔薇は、綺麗なものには棘がある、と美の2面性の代名詞としてよく挙げられる。その大振りで真っ赤な花弁は血を連想させるからか悲しいほどに美しい。『豊饒の海』第1巻春の雪の舞台となった洋館のモデルである鎌倉文学館は、庭園のバラ園で名高い。過ごしやすくなる10月、薔薇の芳香と三島の小説世界を追体験しに行ってみてはどうだろうか。きっと耽美な時を過ごせるはずだ。
by writer Mitsuhiro Ebihara